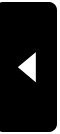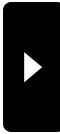2006年11月03日
今度は園児が講談に挑戦!! 「第二部」スタート
コンサートの第二部は、地元島幼稚園の園児たちが、上方講談師「旭堂南左衛門」とその弟子「旭堂南青」との講談の掛け合いに挑戦!!
園児の大半は、まだひらがなも読めない3歳児さん。
でも、なんのその!
セリフもばっちり憶えて、堂々とした元気いっぱいの語り口は、公家役も堂に入ったもの。
南左衛門さんも舌を巻く大活躍ぶりに、これは将来が楽しみ?!
2006年11月03日
船上見学会日記コンクール表彰式
夏休みに安土・近江八幡の小学6年生が水郷めぐりの船に乗って水郷を探検!
地域の歴史や文化のこと、水質や生態系やゴミの問題のことなど、感じ取ったことを日記にしたため、優秀作品にかがやいた10名が、権座の舞台で表彰されました。一人でも多くの子供たちが、水郷のすばらしさ、大切さ、守っていこうという決意をいつまでも心にとどめていてくれたら、と願います。
作品はワークショップテントのならびに掲示され、多くのお客さんが立ち寄って読み入っていました。
2006年11月03日
ぶ~ぶ~楽しいヨシ笛づくり
「ヨシ文化体験」ワークショップのテントでは、地元円山産のヨシを使って簡単に作れるヨシ笛「ぶ~ぶ~笛」づくりが子供たちに大盛況。
予想以上の人出に、スタッフが不足してテンヤワンヤな現場でしたが、慣れないナイフを使って、音が鳴るまで根気強く工作に興じる子供たちの真剣なまなざしや、音が鳴って満面の笑みを浮かべながら得意げに笛を加える子供たちの姿を見るたびに、こちらも嬉しくなってしまいます。
もっとも、コンサートに陶酔したかったお客さんには、横からぶ~ぶ~と鳴る音でご迷惑をおかけしてしまったかも...。
2006年11月03日
もち米からできるのはモチだけじゃない!!
「農文化体験」ワークショップのテントでは、地元営農組合の面々が、地元でとれた新米もち米を昔ながらの杵と臼でつく「餅つき」を披露!!
ご自慢のあんこを乗せたつきたての美味しいお餅がお客さんに振舞われました。



そして、そのすぐ横では、そのもち米のワラを叩いてやわらかくし、「縄編み機」に通すワラ縄づくりも実演!!
もち米のワラは柔らかくて丈が長いので縄を編みやすいんだそうです。
自給自足だった頃は、冬場の農閑期に作る縄は貴重な収入源だったとか。
当時、縄といえば、日常生活から神事まであらゆる場面で登場する、農耕文化の必須アイテム。
ちなみにこの「縄編み機」、壊れて動かなかったものを、持ち主のおじいちゃんが油を差し、部品を買い集めて修理して、当日までに何とか動くようになったもの。
ホント貴重です!!!





ご自慢のあんこを乗せたつきたての美味しいお餅がお客さんに振舞われました。
そして、そのすぐ横では、そのもち米のワラを叩いてやわらかくし、「縄編み機」に通すワラ縄づくりも実演!!
もち米のワラは柔らかくて丈が長いので縄を編みやすいんだそうです。
自給自足だった頃は、冬場の農閑期に作る縄は貴重な収入源だったとか。
当時、縄といえば、日常生活から神事まであらゆる場面で登場する、農耕文化の必須アイテム。
ちなみにこの「縄編み機」、壊れて動かなかったものを、持ち主のおじいちゃんが油を差し、部品を買い集めて修理して、当日までに何とか動くようになったもの。
ホント貴重です!!!
2006年11月03日
湖、水、貝を熱く語る漁師
「西の湖の漁体験」ワークショップでは、安土の元漁師・奥田修三氏を講師に招いて、たくさんの写真や昔の漁具を展示したり、実際に奥田さんの船に乗って話を聞きながら西の湖をめぐったり。
昔は西の湖にたくさんいた巨大な「イケチョウ貝」が、ヨシよりもずっと優れた湖水浄化能力を持っていることを、実際に水槽を使って実証。本当ににごった水がきれいになっていました。
いやはやとにかく、高齢を全く感じさせない奥田さんのパワフルなトークには脱帽。
あの熱意を、権座を通じて、ひとりでも多くの方に伝えられたことがなによりの幸せ。